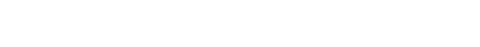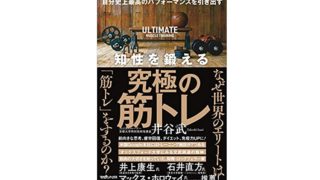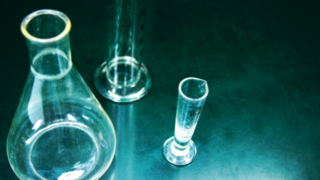自己学習に関して管理人が気づいたことを投稿していきます。
「トム・アミアーノ(1941~)」

サンフランシスコ統一学区の小学校教諭であるトム・アミアーノさんはゲイやレズビアンの教師たちにきちんとした雇用保障がないことに抗議するため、1975年カリフォルニアの先生として初めて公的にカムアウトし、他の教師たちと一緒に地区の教育委員会に対する抗議のピケを張りました。教育委員会は全会一致でLGBTの職員にも雇用保証規定を追加することを決めました。その後、教育委員会委員に立候補、当選し、市教委の長になった後、2008年にはカリフォルニア州下院議員に当選します。
そのトム・アミアーノさんは1993年1月に「府中青年の家」裁判において東京地裁で証言台に立ちます。
「府中青年の家」裁判
1990年、LGBT団体が東京都の「府中青年の家」で合宿利用中に、他団体から差別・嫌がらせを受けました。施設所長に、嫌がらせに対処するよう要請しましたが、所長は「同性愛者の施設利用は今後お断りする」と発言、東京都教育委員会(石川忠雄委員長)も同性愛者の宿泊利用を拒否しました。
LGBT団体は都教委決定を不服として東京都を提訴、東京都は「男女別室ルール」を楯に反論してきました。ところが、調べてみると、男女でも泊めている施設があったり、「男女の部屋割りはグループの責任に任せる」と規則に書いてある施設があることが判明。トム・アミアーノさんも東京地裁で説得力ある証言をしてくれたそうです。国を超えて連帯し合えることは本当に素晴らしいです。とても励まされますね。
1)従来の抗がん剤
 細胞のDNA複製を阻害。「代謝拮抗剤」「アルキル化剤」「白金製剤」などがあり、延命効果のみ。
細胞のDNA複製を阻害。「代謝拮抗剤」「アルキル化剤」「白金製剤」などがあり、延命効果のみ。
2)分子標的薬
異常なたんぱく質と結合して、がん細胞の増殖を止める。同じタイプの遺伝子変異なら、臓器が違っても同じ薬が効く可能性があるので、がん治療を、臓器別から遺伝子変異別に変える必要があるが、「適応拡大」(違う臓器のガンにも使用すること)には、日本では厚生労働省の承認が必要。ただし、有効性だけ確認し、安全性の確認は不要なので承認のハードルは低い。
3)免疫チェックポイント阻害薬
がん細胞は自分を攻撃する免疫に対してブレーキをかけようとするが、この薬はブレーキを掛けさせないように働き、免疫をふたたび活性化させる。
①CSIS(戦略国際問題研究所) 最も影響力の強いシンクタンク。
日本政府から資金援助を受けて「アーミテージ・ナイ報告書」を発行している。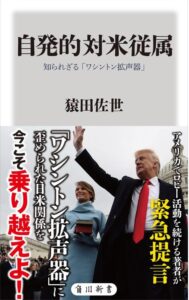
援助している団体・個人の顔ぶれがすごい。
笹川平和財団、三菱商事、経団連、NTT、富士通、丸紅、キャノン、日立、
ホンダ、伊藤忠、三菱重工、三井物産、双日、住友商事、三井住友銀行、トヨタ、
稲盛和夫氏(ビル建て替え費負担)
客員研究員送り出ししている団体・個人として、
丸紅、JETRO、富士通、防衛省、朝日新聞、経団連、公安調査庁、NEC、警察庁、
東京海上火災、内閣官房、NTTデータ、小泉進次郎氏
②CFR(外交問題評議会) 「フォーリン・アフェアーズ」を発行
③AEI(アメリカン・エンタープライズ公共政策研究所) チェイニーが理事
④ヘリテージ財団 トランプ政権移行をサポートした保守的シンクタンク
⑤カーネギー国際平和基金
⑥ブルッキングス研究所 資金提供:国際交流基金日米センター、JICA、日本大使館、航空自衛隊、
国際協力銀行、トヨタ、全日空、日立財団、三菱商事、日経、
野村財団、UFJ、ホンダ、国際経済交流財団、丸紅、三菱重工、
三井物産、双日、住友商事、三井住友銀行など
⑦米国先端研究所
①リチャード・アーミテージ 共和党。レーガン政権で国防次官補。ブッシュJr政権で国務副長官。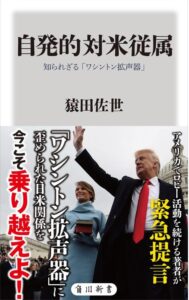
②ジョン・ハムレ クリントン政権で国防次官、国防副長官。シンクタンクCSISの所長。
③マイケル・グリーン ブッシュJr政権で国家安全保障会議(NSC)アジア上級部長。CSISの上級副所長兼日本部長
④ジョセフ・ナイ 民主党。クリントン政権で、CIA直属のNIC(国家情報会議)議長(次官級)、国防次補。現在はハーバード大学特別功労教授
⑤カート・キャンベル オバマ政権で国務次官補(東アジア・太平洋担当)。
マルクスの資本主義分析は非常に鋭かった→それゆえ「資本主義社会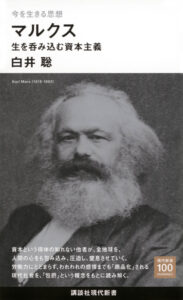 が革命で崩壊するという結論」に注目が集まりすぎた→資本家から財産を没収して公有化するなどの人格的次元で革命を起こした→ソ連崩壊や中国の市場経済移行など、社会主義は失敗した。
が革命で崩壊するという結論」に注目が集まりすぎた→資本家から財産を没収して公有化するなどの人格的次元で革命を起こした→ソ連崩壊や中国の市場経済移行など、社会主義は失敗した。
そもそもマルクスは「資本の他者性」を見抜いていた→人格的次元での批判では資本主義は崩壊しない→資本主義が崩れるのはそれ自身が持つ内部矛盾によってのみである→行き過ぎたグローバリゼーション、新自由主義などの弊害が生じている→マルクスの言う「包摂」の深化が顕在化している!→再び注目が集まった。
包摂=資本主義システムが人間の全存在を含むすべて、自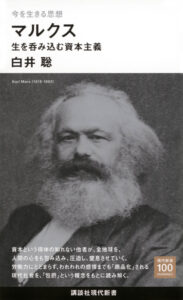 然環境を含む地球全体を包み込むこと
然環境を含む地球全体を包み込むこと
資本とは価値増殖の無限運動ですが、自然全体が「価値」という得体のしれない何かに包み込まれ、増殖するための手段にされてしまうのです。
だが、技術革新や発明は、人間の幸福を目的としたものではない。資本自身の内在的衝動であるとマルクスは分析する。資本は人間の道徳的意図や幸福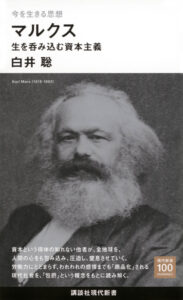 への願望とはまったく無関係のロジックを持っており、それによって運動している。
への願望とはまったく無関係のロジックを持っており、それによって運動している。
資本は、ただ盲目的な、無制限の価値増殖の運動でしかない。
これが「資本の他者性」なのだとマルクスは見抜きます。さらに「他人である資本」は「消費社会」と「法人」を生み出しました。
ワクチン開発には「確かに安全であり、予防効果がある」ということを数千人レベルで確認する第三相試験が必要です。ところがコロナワクチンの場合、日本国内の臨床試験の母数は、ワクチン接種群でわずか119人、プラシボー群はさらに少ない41人でした。
PMDAワクチン等審査部は2020年9月2日、文書を出し、「海外で第三相試験が実施されていれば、国内では日本人における免疫原性及び安全性を確認する国内臨床試験(第一、第二相試験)で十分」としています。
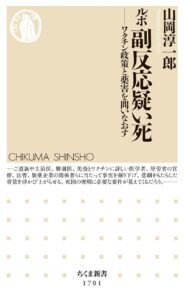
2000年代の初めのころまで日本は新薬の承認審査に時間がかかり、海外で使われている医薬品が国内で未承認状態の「ドラッグ・ラグ」が問題視され、多くの患者が海外から高額の未承認薬を取り寄せていました。
そこに日本の市場開放、規制緩和を求める米国政府が圧力を加えました。米国は2011年の「日米経済調和対話」で「新薬創出加算(*注2)を恒久化し、ドラッグ・ラグ解消を促進し、研究開発への誘因を強化せよ」と圧力を掛けてきたのです。「海外の治験データを流用し、PMDAは製薬会社と連携して承認審査を行え」と。
・・・・
厚労省は海外で先行したワクチンの第三相試験の国内実施を免除する一方、国産ワクチン開発には従来どおりの第三相試験を求めました。後発の開発者がプラシボーを被験者に打って新型コロナに感染させるのは許されるのか? という倫理的問題もあり、国産開発は挫折しました。
・・・・
結果、利用できるワクチンが欧米から20年遅れになる「ワクチン・ギャップ」(WHOが推奨するワクチンが、国内では公的な定期接種に組み込まれず、国際的水準に届いていない状態)が生じてしまいました。
これに対して、国は反論しましたが、1984年東京地裁、1992年東京高裁での原告側の勝訴などの結果、国は予防接種行政の方針を大転換。「義務」から「努力義務」に、「集団」から「個別」へと接種形態を変えました。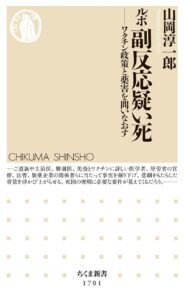
非加熱製剤販売元のミドリ十字は加熱製剤が承認された後もすぐに非加熱製剤を回収せずHIV感染を拡大させ、回収を命じなかった厚生省も不作為責任を問われ、当時の担当者が業務上過失致死で有罪になりました。
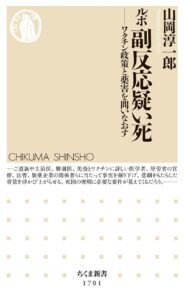
ところがほぼ同時期、やはり非加熱製剤の血液凝固因子製剤「フィブリノゲン」がC型肝炎ウイルスに汚染されていたため薬害が広がりました。この製造販売者もミドリ十字でした。
ミドリ十字は戦中に中国大陸で細菌戦や人体実験を行なった731部隊の生き残りで元陸軍軍医の内藤良一が創設した会社でした。内藤は、厚生省薬務局の天下り官僚を迎え、要職に就けました。経営の実態を握った元官僚たちは判断を誤り、元薬務局長の松下廉蔵は薬害エイズ事件で禁固刑に処せられました。「フィブリノゲン」も米FDAが承認を取り消した後も日本国内で使われ被害が広がっています。
厚労省は2002年に縦割り組織の連携不足を指摘した報告書をまとめ、「小さな政府」を目指す小泉純一郎内閣の「聖域なき構造改革」の特殊法人改革の流れにのって、PMDAが設立されたというわけです。
①副反応疑い報告制度
医療機関からPMDAに伝えられ、PMDAが判定を下し、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の公開資料にリストアップし、公表されます。集まったデータをもとにワクチン接種を継続するかどうか決めるのが目的です。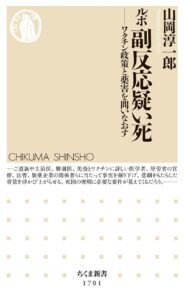
②予防接種健康被害救済制度
健康被害者や遺族が自治体の窓口に補償請求の申請をします。国に取り次がれ、審査会の審査を経て、死亡一時金や葬祭料が支給されます。健康被害者を迅速に幅広く救うのが目的です。
熊本県は1997年、「3年連続して水俣湾内の魚介類が基準値を下回った」として安全宣言を出し、仕切り網を撤去、漁業が自由になります。その後、熊本県は毎年魚の水銀値を測定していき、2004年の調査ではカサゴのメチル水銀値が0.36PPMでしたが、総水銀規制値の0.4PPMは超えないと判断します。これに対して国立水俣病総合研究センターの松山明人センターリスク評価室長らがカサゴを含む3魚種で測定した結果は、平均で0.42PPMでした。なぜ、このような差が生じたのでしょう?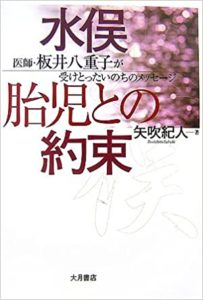
熊本県の調査は「公定法」、松山室長らの調査は「赤木法」と、???測定方法で行われたためだったからです。その後、1969年から30年以上たった2004年に行われたテレビのインタビューで、熊本県が設置した検討会議の会長をつとめた、いわゆる学会の権威が「メチル水銀がどこでできるかわからない」などというトンデモ発言をし、本書で痛烈に批判されています。
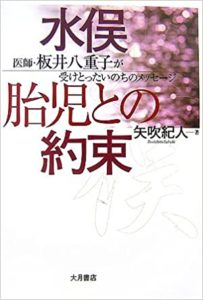 化石燃料の燃焼による大気中への水銀の放出は一番の問題なのだそうです。水銀は自然界のなかでメチル化(メチレーション)し、食物連鎖を通じて人間に大きな影響を与えます。そして何よりも恐ろしいのが、妊婦の体内に入り込み、胎盤を通じて胎児に移行してしまうことです。
化石燃料の燃焼による大気中への水銀の放出は一番の問題なのだそうです。水銀は自然界のなかでメチル化(メチレーション)し、食物連鎖を通じて人間に大きな影響を与えます。そして何よりも恐ろしいのが、妊婦の体内に入り込み、胎盤を通じて胎児に移行してしまうことです。
・・・・
食物連鎖は魚同士でも起こります。より大型の魚は小型の魚を食べることで体内のメチル水銀濃度が高くなります。
・・・・
日本では、熊本県の委託を受けて熊本大学が研究、1973年に県知事に提言したことで、「水銀パニック」が日本中に起こったため、急遽、事態を沈静化させる目的で厚生省が、
・「魚介類中の水銀をメチル水銀で0.3PPM、総水銀で0.4PPM」
という暫定基準を定めるに留まっていました。
・世界的な「胎児保護」の圧力を受け、2003年になって初めて、厚労省薬事食品衛生審議会は「1回の食事量を60~80g、バンドウイルカは2ヶ月に1回以下、ツチクジラ、コビレゴンドウ、マッコウクジラ、サメ(筋肉)は週に1回以下、メカジキ、キンメダイは週2回以下」という魚介類摂取制限勧告を出した。これにはマグロ類が含まれていませんでした。
・各界からの指摘を受け、厚労省は2005年に「クロマグロ」「メバチマグロ」「クロムツ」などの9種類の魚類を追加しました。
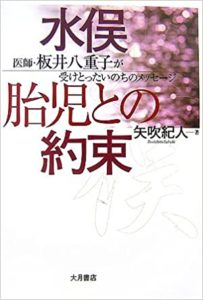 メチル水銀(有機水銀の一つ。水俣病の原因として同一に語られる)は、アミノ酸の一種である「システィン」と結合することができます。システィンは脳や胎児時の発達に必要な物質なので、これと結合したメチル水銀も脳血液関門や胎盤を容易に通過してしまいます。これは、他の重金属類ではみられない特性なのだそうです。
メチル水銀(有機水銀の一つ。水俣病の原因として同一に語られる)は、アミノ酸の一種である「システィン」と結合することができます。システィンは脳や胎児時の発達に必要な物質なので、これと結合したメチル水銀も脳血液関門や胎盤を容易に通過してしまいます。これは、他の重金属類ではみられない特性なのだそうです。
さらに悲しいことに、母体のような排泄経路を持たない胎児は、母体よりメチル水銀の蓄積が起こりやすいため、妊婦のほうが非妊婦より血中メチル水銀濃度が低くなってしまうのだそうです。母親にとって何よりも大事な胎児が母親の分まで有機水銀を吸収してしまうなんて。こんな辛いことがあるでしょうか……。
原因の一つは、
マグロなどの大型魚を多量に消費する県民性にあるのではないかといわれている。
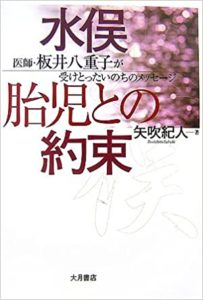
大気中や海洋中などに放出された水銀は食物連鎖によって蓄積され、魚介類、なかでも食物連鎖の
上位にいる肉食性の大型魚に大量に蓄積されていく。これらの魚類を多食する人
びとに、有機水銀の
「長期微量汚染」の影響が出る可能性が指摘されている
人の悪口を言わず、その人について知っているよい面を話す。
人は誰でも「自分は重要である」と感じることを好む。
人は「賞賛」に飢えている。お世辞でなく、正直な、真実の「賞賛」に飢えている。
野球選手時代に私は「非難」は選手を傷つける以外、決して何の役にも立たない、ということを知った。逆に、「正直な賞賛と激励」が平凡な選手をスターにすることも知った。
野球選手引退後、この信条は事業においても、「家庭」においても同じ結果をもたらすことを知った。
フランクリンの指導方法をフランクに伝授したデール・カーネギーの言葉
人間が偉大であればあるほど「より話がしやすく」、より「慎ましやか」であり、より人間的である。
自分が高慢で人から嫌われていると知ったフランクリンは12の信条に「謙譲の徳」を付け加えました。
セントラルパークに集まった新たに帰化した市民たちに語ったラーニド・ハンド判事の言葉
自由の精神とは「自分が正しいとあくまで言い張らない」精神です。「他の人びとの心を理解しようとする」精神です。……「少数者も多数者と並んで聞き入れられ考慮される」神の国があるということを教えたキリストの精神なのです。
あなたの話し相手は機知のあることを言って、あなたに喜ばれたいからこそ、あなたにまた会いたいと思うものである。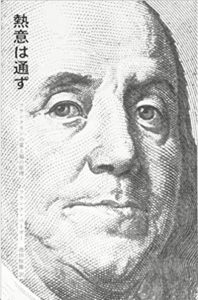
相手が「何に興味を持っているか」を知ること。
相手が「喜んで答えられらるような質問」をし、その話をするように導く。
それから、「相手の話に聞き入る」。
キリストは「3年の伝道期間」、「人の悩みを聞くこと」に費やした。
相手の話に興味を持っていることを態度で示すべし。会話に集中し、心から賞賛せよ。それこそが誰もが切に求めながらも、なかなか得られないものである。熱心に聞き入るべし。
「セリング(Selling)」とは「話術」であり、「売り手」は「脚色家」である。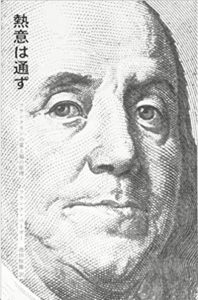
「聞き手の直面する問題」に「ぴったり即応する話」をする。
聞き手は「解決策が聞きたくて」一生懸命になる。
相手に語らせるには「機転の利いた1,2の質問」をする。
「こちらが話すこと」は「相手が話したいと思うこと」の「半分の興味」も与えられない。